| ホームページ★ 峠と旅 ★ |
さじきとうげ (峠と旅 No.239)
落合峠と共に東祖谷山村の落合へと越える祖谷街道の峠道
(掲載 2015. 8. 6 最終峠走行 2015. 5.28)
| |
 |
切通しの奥は徳島県東みよし町西庄(にししょう)/奥森清(おくもりきよ)
(旧三好郡三加茂町(みかもちょう)西庄)
手前は同県三好市東祖谷落合(ひがしいやおちあい)/深渕(みぶち)
(旧三好郡東祖谷山村(ひがしいややまそん)落合)
道は県道(主要地方道)44号・三加茂東祖谷山線
標高は1,020〜1,030m (地形図の等高線より)
現在の棧敷峠は車一台がやっと通れる狭い切通し
頭上の木々も覆いかぶさり、まるでトンネルのよう
この暗い切通しを旧三加茂町側に抜けた真正面に
以前は広い眺めがあった
しかし、今は生い茂った木々が遮ってしまっている
| 序 |
|
<22年前> 1993年の春、落合峠に続いてこの棧敷峠を一度だけ越えたことがある。 東京の自宅と四国との往復も含め、僅か5日間の旅程で、ひたすらジムニーで走り回るばかりの旅でのことだった。 まだ未舗装路を残す険しい落合峠に比べると、棧敷峠はその付属の峠道のような気がして、ほとんど立ち止まることなく走り抜けた。 今思い返しても記憶に残ることはあまりない。 ただ、一つだけ印象的なことがあった。峠の暗く狭い切通しを旧三加茂町側に抜けると、パッと目の前が開けた。 幾重かに連なる山並みの向こうに四国の大河・吉野川が流れる平地が望める。ジムニーに乗りながらも、さすがにその景色は写真に収めたのだった(下の写真)。 それ以外は、棧敷峠に関する写真は一枚も残っていない。 時を経るに従い、この棧敷峠のことが気になりだした。一体どんな峠道だったのだろうか。もう一度じっくり旅をしてみたいと思い出した。 その機会がやっと今年(2015年)に訪れた。 |
 |
旧三加茂町方向を望む
「風呂塔(ふろとう)キャンプ場 3km 三加茂町」と書かれた矢印看板がポツンと立つ
| <峠名> 棧敷(さじき)峠とはなかなか味のある峠名だ。「棧敷峠」または「桟敷峠」と書かれる。 一冊の本の中で「棧敷」と「桟敷」が混在して用いられているのも見掛ける。 古いツーリングマップでは「浅敷峠」と書かれていたが、これはさすがに誤植であろう。 後のツーリングマップルでは「棧敷峠」に変わっていた。 「棧」でも「桟」でもどちらでも構わないようだが、 国土地理院の地形図(ウェブ地図、地理院地図)で「桟敷峠」と検索したら何もヒットしない。 不思議に思って峠のある部分を探し出すと「棧敷峠」の方で掲載されていた。こういう点は微妙である。 「棧」の方が古い漢字で、最近は「桟」の字が一般に用いられるようにも思える。ここでは国土地理院にならって「棧敷峠」と記すこととした。 <「棧敷」の意味> 文献(角川日本地名大辞典)などを調べても、残念ながらこの峠名の由来は分からなかった。 一般的な「棧敷」の意味は、板敷きの少し高い所に設けられた見物席などを指す。上等な観客席のことだ。桟敷席とか天井桟敷という言葉がある。 初めて棧敷峠を訪れ、峠からの眺めを目にした時は、この素晴らしい景色を鑑賞する棧敷席という意味で、この名があるのだろうと思った。 しかし、その後、何の証拠も見付からない。 「さじき」と呼ばれるようになったのには、それなりの起源があるのだろう。しかし、こうした峠名には当て字が多いので困る。 必ずしも現在使われる「棧敷」が意味するような由来があったとは限らない。 ただ、付近に棧敷という地名も見当たらず、この峠に付けられた固有の名前ではあろう。 |
| <所在> 棧敷峠は徳島県の東みよし町と三好市との境に位置する。どちらも「みよし」で、この新しい市町名では広過ぎて分かり難い。 以前の三加茂町(みかもちょう)と東祖谷山村(ひがしいややまそん)の境である。徳島県の中では比較的西の方に位置する。 <旧三加茂町> 旧三加茂町は東西方向に流れる吉野川の右岸に広がり、町のほぼ中央を加茂谷川(かもだにがわ)が北流、吉野川に注いでいる。 市街地は加茂谷川を中心に扇状に広がった平坦地に形成されている。加茂谷川上流部に位置する棧敷峠からは、その扇状地の様子がうかがえるのだ。 旧三加茂町は、縄文・弥生時代の遺物・遺跡が発見され、古墳なども確認されており、古代より人が住み着いていた地であるとのこと。 そうした人の暮らしが連綿と営まれ、今の三加茂市街の発展へと続いてきたのかと思わせる。 |
| <地形図(参考)> 国土地理院の 地形図にリンクします。 (上の地図は、マウスによる拡大・縮小、移動ができます) |
|
<旧東祖谷山村> 棧敷峠には、四国第二の高峰・剣山(1955m)から北西方向に派生した稜線が延びてきている。剣山地の北西端に位置する。峠の南側は旧東祖谷山村である。 旧西祖谷山村と共に剣山を源とする祖谷川(いやがわ)沿いに小さな集落が点在する山村だ。 「祖谷」は平家の落人伝説を持ち、秘境の代名詞ともいえる。 しかし、棧敷峠を越えても、まだ祖谷川沿いではない。 その支流の松尾川の上流部となる。そこに深淵(みぶち、深渕とも)と呼ばれる山間部の集落がある。棧敷峠はその深淵へと至る峠道だ。 |
|
<祖谷街道> 棧敷峠は何となく釈然としない峠道に思えていた。現在、深淵より松尾川沿いに下る車道は存在しないのだ。 深淵からは更に南の落合峠を越えると、やっと祖谷川沿いに至る。 棧敷峠と落合峠をセットにしないと、道としてあまり機能しないのだ。一本の峠道としては美しい形ではない。 このことは古くから同じ事情だったようで、開けた吉野川沿いと険しい祖谷川沿いを結ぶ祖谷街道(祖谷道とも)して、 棧敷峠と落合峠の2つの峠を続けて越える道筋が使われたそうだ。 祖谷街道として他には小島峠(おしま)などもその一つとのこと。 現在は見ノ越(みのこし)から祖谷川沿いに国道439号が下り、 途中からは県道32号が祖谷川沿いに通じ、これが祖谷の地と外界を結ぶ幹線路となっている。 しかし、こうした祖谷川沿いに道が発達したのは後のことで、往時は吉野川と祖谷川を隔てる山並みを越え、祖谷の奥地へと生活必需品の塩などを運搬したようだ。 棧敷峠はその祖谷街道としての要路であった。 |
| <日本百名峠(余談)> 棧敷峠は井出孫六氏編纂の「日本百名峠」の一つに選ばれている。 執筆者の一人の藤崎康夫氏は棧敷峠の項で、峠から望む景色を「棧敷から見る舞台のよう」と記している。 やはり誰しも峠からの眺望と峠名との関連を思うようだが、峠名の由来かどうかは依然不明である。 ところで、「日本百名峠」ではどのような理由でこの棧敷峠を選んだのだろうか。 峠の実用面として、祖谷街道としての棧敷峠を評価したようではなさそうだ。 また、峠の切通しなどの形や地形などもあまり関係してないように思う。 一方、深田久弥氏の「日本百名山」では、まず開聞岳を除いて標高1,000m以上の山の中から選び、そして山を登山の対象として評価しているようである。 では、峠は何の対象であろうか。 自分にとっては「旅」の対象である。峠道を旅して面白いかどうかだ。見事なV字の切通しは美しいと思う。 道はちょっと険しい方が走り切った時の達成感が増す。道の途中での景観は安らぎを与えてくれる。 歴史的背景は旅の味わいになる。いろいろな観点があるが、旅は個々人の趣向が強く、誰しもが納得できる評価基準などありそうにない。 また、山と違って峠は道という交通手段としての実用面を持つが、まさか交通量でランク付けしても始まらない。 「日本百名峠」では、一つには現在における知名度で峠を選んでいる面があるように思う。それには歴史的背景などが大きく影響しているだろう。 しかし、「日本百名峠」の内容を読むと、その峠を実際に訪れた方の思い入れが強く出ている気がする。 棧敷峠を再び訪れたかったのは、「日本百名峠」に選ばれた峠がどんな峠だったか、もう一度自分の目で確かめたかったからでもある。 今回、改めて自分なりに峠をとらえることができた。 あくまで「個人的な感想」としか説明がつかないが、それでもあえて言わせてもらうと、この棧敷峠は自分にとっての200名峠か、 少なくとも300名峠の中には入るような気がする。因みに、お隣の落合峠は断然百名峠だ。 一度、自分なりの峠選定基準を設け、自分なりの百名峠を選んでみたいと思うのだが、きっと徒労に終わることだろう。 |
| 旧三加茂町より峠へ |
|
<国道192号> 四国の吉野川は日本三大暴れ川の一つだそうで、過去に氾濫の歴史が多い。その為、古代より人は山裾の方に住み着いたそうだ。 現在、吉野川沿いに通じる国道192号・伊予街道も、比較的最近になって整備された道だそうで、昭和46年とか50年の貫通とのこと。 今ではそれに加え、徳島自動車道が開通している。JR徳島線も通じ、この吉野川沿いの交通は、四国の中でも発達したものの一つに思える。 <県道44号> その国道192号から分かれて棧敷峠を越えるのは、県道(主要地方道)44号・三加茂東祖谷山線だ。 初めて棧敷峠を旧三加茂町側に下って来た時は、峠を越える県道が加茂谷川沿いをそのままに国道192号へと接続していた。 ところが最近の道路地図を見ると、県道44号はJR徳島線の阿波加茂駅の前を迂回して通る。何とも変則的なコースだ。 国道からは「東みよし町北村」という交差点より分岐するらしい。とにかくその県道沿いに進もうとしたら、あえなく分岐を見落とした。 |
 |
「東みよし町北村」の交差点(徳島市方向に見る)
ここで右折する筈が、通り過ぎてしまった
 加茂銀座街を抜ける (撮影 2015. 5.28) 正面が阿波加茂駅前 左右に通じるのが県道44号 |
<阿波加茂駅> 四国に関する地図は1997年発行のツーリングマップルしか手持ちがなかった。 今回の四国の旅に先立ち、四国全県について詳しい県別マップルを買い揃えようかと妻に相談したが、 勿体ないから数年前に買ったカーナビで済ませましょうということになってしまった。 国道沿いの看板を眺めていると、「三好市」だとか「東みよし町」だとか、見慣れない地名ばかりだ。 古いツーリングマップルを見ながら、今はどの辺りだろうかと思っていると、気が付いた時は県道が分岐する交差点を通り過ぎていたのだ。 慌てて阿波加茂駅への案内看板に従い、狭い道に入り込む。すると、加茂銀座街と掲げられた看板を抜けて阿波加茂駅の駅前広場に出た。 その駅前を東西に通じているのが県道44号だ。 |
 |
|
<徳島線を渡る> 旅先では何の目的もなく駅に立ち寄ることが多い。駅舎を眺めたり、改札口をのぞいたり、時には有益な案合看板を見付けたりする。 でも、棧敷峠から落合峠と続く峠の旅は長い。素朴な阿波加茂駅の駅舎が気になりながらも、駅前に通じる県道44号を進む。 道は線路沿いに少し進むと、直角に曲がって線路を越えるように道路看板が出て来る。 直進は「三加茂町役場」とあったが、今は正確には「東みよし町役場」であろう。 一方、右に曲がる県道の行先には早くも「深渕」(みぶち)とある。棧敷峠を越えた先の旧東祖谷山村側にある地名となる。 この付近の道は路地のように狭いが、間違いなく峠を越えて行く道であることを示している。 |
 この先右に曲がって徳島線を渡る (撮影 2015. 5.28) |
 県道44号 (撮影 2015. 5.28) のどかな道 |
<踏切以降> 踏切を渡って徳島線の南側に出ると、付近一帯に広がる住宅地の中を縫って狭い道が続く。軽自動車同士でもすれ違いが難しそうな道だ。 とても主要地方道とは思えない。これがもう峠近くの辺ぴな場所ならいざ知らず、ここはまだ駅至近の住宅街である。 ただ、幹線路の国道沿いの市街地からは外れているので、田んぼなども時折見掛けるのどかな所だ。 |
|
<十字路> 突如、狭い十字路に出くわす。主要地方道である筈のこちらが一旦停止である。何の標識もない。 南へ向かえばいいので、ここは右折と判断できるが、やはり変則的な道筋である。 |
 十字路 (撮影 2015. 5.28) ここを右折 |
 加茂谷川左岸沿いの道 (撮影 2015. 5.28) |
<加茂谷川左岸> 十字路を曲がると道はほぼ南を指し、地図上では加茂谷川の左岸に沿っている。初めて棧敷峠を越えた来た時は、この道に沿って真っ直ぐ国道まで抜けた筈である。 今でもそちらの方が素直な道筋に思えるが、どういう訳か主要地方道は阿波加茂駅を経由したかったようだ。 <案内看板> 加茂谷川が左手に見えて来ると、直ぐに右への分岐がある(下の写真)。角に案内看板が立つ。右折方向に「加茂農村公園」とある。 直進は「風呂塔キャンプ場 15K」などと書かれている。 |
 右手に分岐 (撮影 2015. 5.28) 角に案内看板が立つ |
 案内看板 (撮影 2015. 5.28) |
|
<風呂塔> 風呂塔とは棧敷峠から南東方向にもう1km程登った稜線上にある1,401.6mの山で、「ふろのとう」とか「ふろんとう」とも呼ばれるようだ。 山の北麓に風呂塔キャンプ場があるようで、棧敷峠経由でキャンプ場近くまで車道が延びる。また、棧敷峠からは稜線上を行く登山道が始まっている。 峠にある看板では風呂塔キャンプ場まで3kmとあるので、ここから峠までは12kmとなる。 看板の立つ分岐を過ぎると、道はそろそろ加茂谷川の谷間へと入って行く。右手は崖がそびえたつ。 <道路看板> 道路看板が出てきて、また主要地方道が曲がることを示していた(下の写真)。直進は「山根東」、主要地方道は左折して行先は「深渕」(みぶち)とある。 本来、県道(主要地方道)44号・三加茂東祖谷山線はその名の通り旧三加茂町の市街と旧東祖谷山村の落合集落とを結ぶ道だ。 しかし、今もって落合峠の前後は林道深淵落合線によって繋がっている。その為か、県道44号の行先は落合峠の手前の「深渕」になっているようだ。 |
 道路看板 (撮影 2015. 5.28) |
 県道は左折 (撮影 2015. 5.28) |
|
谷がいよいよ狭まってきたこともあって、道は狭く人家の軒先をかすめるようにして進む。こういう時に限って対向車が来る。
お互いに路肩にはみ出すようにして軽トラ一台とすれ違った。 |
 |
|
<加茂谷川右岸へ> 県道は道なりに左折して加茂谷川を渡る。橋の上からは川面が眺められた。この水が棧敷峠の方から流れ下ってきているのだ。 |
 ここで県道は道なりに左折 (撮影 2015. 5.28) 直ぐに加茂谷川を渡る |
 加茂谷川を渡る (撮影 2015. 5.28) |
 橋の上より川の上流方向を望む (撮影 2015. 5.28) |
|
<T字路> 加茂谷川右岸に出るとT字路に突き当たる。全く右左折が多い県道だ。この分岐には看板が完備され、右折が県道44号、左折は県道264号と出ている。 264号の看板は黄色で一般の県道を意味し、44号の方は緑色で主要地方道を表しているようだ。 ここから分かれる県道264号は国道192号の方へ戻って行く。 |
 T字路 (撮影 2015. 5.28) 県道44号はここを右折 |
 左折は県道264号 (撮影 2015. 5.28) |
 鍛冶屋敷集落内 (撮影 2015. 5.28) 右手に西庄郵便局 |
<西庄> 道が右岸沿いになってから大字西庄(にししょう)になる。吉野川沿いの一部分から始まり峠の稜線までが広く西庄の地だ。 江戸期から明治22年まで西庄村、その後三庄村の大字、昭和34年から三加茂町の大字となる。 <鍛冶屋敷> 道は西庄の鍛冶屋敷という集落内を進む。もうこの付近では幹線路であるこの県道以外に道らしい道は通じず、県道の両側にのみ建物が並ぶようになる。 道幅は依然狭い。郵便局の西庄局が人家に並んで立っていた。 |
 |
|
<再び左岸沿い> 道はクランク状に加茂谷川を渡り、元の左岸沿いになる。加茂山口というバス停を過ぎると、一時的に人家が途切れる。 加茂谷川の谷は完全に狭まり、この先は川の蛇行が始まる。旧三加茂町は鍛冶屋敷付近を頂点として吉野川方面に広がる扇状地を成す。 |
 加茂山口のバス停 (撮影 2015. 5.28) |
 加茂山口付近 (撮影 2015. 5.28) この先で人家が途切れる |
| 加茂谷川の谷間へ |
|
<谷間へ> 鍛冶屋敷集落を後に、狭い谷間を行く寂しい道となる。ただ、この先にも集落は幾つも出て来る。看板にあるように福祉施設などもあるようだ。 しかし、この県道沿いとは限らない。県道から分かれる細い道が所々にあり、その道に入った先にあるらしい。 |
 博愛ヴィレッジ(福祉施設)の看板 (撮影 2015. 5.28) |
 電光掲示板など (撮影 2015. 5.28) |
<電光掲示板など> やや道が険しくなってきたようで、電光掲示板が現れ、「落石の恐れあり 走行注意」と出ていた。 困ったことに県道の工事を示す看板も立っていたが、本日は「解除中」とあり安心する。 <2車線路> 電光掲示板を過ぎると、道はセンターラインもある2車線路に変わった。 国道を分かれてからずっと狭い道だったのが、人家も途切れた渓谷区間に入ってから道幅が広がるというのも皮肉である。 |
 工事看板 (撮影 2015. 5.28) 工事個所は「西庄小の上」とある |
 電光掲示板 (撮影 2015. 5.28) |
|
<加茂山への分岐> 山草園などの看板が出て来ると、その右手に分岐があった。加茂山とか桑内という集落へと登る道だ。福祉施設などもそちらにあるようだ。 地形図を眺めると、その山腹にはいろいろ枝道が延び、人家が無数に点在している。むしろ県道沿いより多くの人家があるようだ。 |
 加茂山分岐付近 (撮影 2015. 5.28) この右手に道が分岐する (写真には入らなかった) |
 山草園の看板 (撮影 2015. 5.28) 右へ5KMとある |
|
「波内」(浪内)のバス停を過ぎると、道は右岸へ渡る。付近は浪内の集落でその付近の県道沿いにも僅かに建屋が見られる。
しかし、殆んどは人気のない2車線路が続く。 |
 右岸沿いの2車線路 (撮影 2015. 5.28) |
 五名下のバス停 (撮影 2015. 5.28) |
地図では県道沿いに横根、五名下という集落を過ぎる。五名下バス停付近では、県道沿いに人家はなく、代わりに左右へと道が分岐する。
そうした道に入った奥に、大きな集落があるようだ。県道からはその様子はうかがいようもない。 |
 |
バス停があるが沿道には人家が見られない
| <狭路部へ> 左手上に新田神社を見た少し先で、2車線路も遂に力尽きる。一挙に狭い道に変わる。ここからは峠を越えた先までセンターラインにはお目に掛かれない。 |
 狭路開始 (撮影 2015. 5.28) |
 右手に加茂谷川を眺める (撮影 2015. 5.28) |
| <対向車> 道は加茂谷川沿いに細々と通じる。川側のガードレールと山側の壁に挟まれ、殆んど車一台分の幅しかない。待避所を過ぎた先で運悪く対向車に出くわす。 僅かな路肩を見付け、そこに乗り入れてやっとかわす。 |
 待避所を過ぎる (撮影 2015. 5.28) |
 運悪く待避所先で対向車 (撮影 2015. 5.28) 丁度山側に路肩有り |
|
<平付近> 狭路区間になってから、県道近辺に比較的建物が多く並ぶ所が一箇所ある。地形図では「平」と集落名が記されている。 郵便局ではないが郵便ポストが立っている。 |
 郵便ポスト (撮影 2015. 5.28) |
 右手上に小学校? (撮影 2015. 5.28) |
<西庄小学校> 加茂谷川対岸の上には学校のような建物も見える。 道路地図によっては「西庄小学校」と記載され、県道沿いのバス停名は「西庄小学校前」となっているものもある。 ただ、地形図には小学校を示す記号は書かれていない。バス停の名前も実際には「谷合下」であった。既に廃校になっているのかもしれない。 |
|
<ここでおよがれん(余談)> 小学校のある方へ渡る橋の袂にバス停が立つ。その直ぐそばに看板が立ち、よく見ると「キケン ここでおよがれん!」とあった。 漢字を使わない、小学生などの子供向けの看板であった。かつては多くの小学生がこの橋を渡って通学していた時代があったのだろう。 それにしても「およがれん」という地方色豊かな言葉がいい感じだ。すましたように「およいではいけません」などというより、余程説得力がありそうである。 学校近辺を過ぎると、また狭く寂しい道に戻る。途中、工事個所があったが看板にあった通り休工中で、無事に通過する。 <左岸へ> 道が幾度目かの加茂谷川を渡り左岸に出ると、その先で少し開けてきた。県道沿いより少し登った所に人家がポツンポツンと立つ。 |
 谷合下バス停 (撮影 2015. 5.28) |
 |
この先少し開ける
| <谷合分岐> 道路看板も立つ分岐が出てきた。行先は何も示されていない。 |
 この先に分岐 (撮影 2015. 5.28) |
 道路看板 (撮影 2015. 5.28) 左が多分新発地へ |
|
分岐には三加茂青年連合会による看板もあるが、中身はかすれてもう読めない。分岐する道の方を望むと、斜面の上の方にまで人家があるのが分かる。
地図を見ると「新発地」(しんぼち)という地名がある。 ここでは2つの道が接続するが、川も2筋の流れがここで合流する。東寄りが棧敷峠から流れ下る加茂谷川で、西寄りがその支流である。 2つの川が合わさる為か、「谷合」という地名が残る。 |
 左へ分岐する道 (撮影 2015. 5.28) その先にも人家 |
 分岐の看板 (撮影 2015. 5.28) |
 左手に支流 (撮影 2015. 5.28) トラックを追い越させる |
<支流沿い> 道は一時的に西寄りの支流沿いに遡る。調べてみると、こちらを「加茂谷川」とし、東側の川を「新発地谷川」(しんはっちだにがわ?)とする地図があった。 新発地集落のある谷なので、「新発地谷川」の名はなる程とも思える。ただ、ここでは地形図の記載に従い、西側を支流、東側を本流としておく。 |
|
<支流を渡る> 西側の支流沿いを進んでいると、こんな所にまで大型トラックがやって来た。今日は道路工事は解除中の筈だが、どうしたことだろうか。 のんびり走りたいので、道幅がちょっと広い場所で追い越してもらった。 すると、その先の支流を渡る橋(西谷橋?)の付近で、何やら住民が大勢集まっている。トラックもそこに停まり、なかなか動かない。 追い越してもらったのはかえって失敗だったかと思っていると、やっとトラックが動き、支流を渡った先で停車した。 橋の付近はちょっとした集落の中心地で、本当は少し立止って様子を見ておきたかったのだが、慌ただしい雰囲気なので、トラックを追い越して先に進む。 |
 西谷橋手前 (撮影 2015. 5.28) |
 西谷橋を渡る (撮影 2015. 5.28) |
| 谷の高みへ |
|
<本流沿いに戻る> 道は西側の支流を少し迂回した後は、また本流沿いへと直ぐに引き返す。しかし、それまでの様子とはちょっと趣向が変わる。 川に沿った谷底ではなく、谷の斜面の少し高みに道が通じる。加茂谷川の谷間に広く視界が開け始め、気分も良い。 道が通る左岸沿いにも、また対岸にもポツリポツリと人家が望める。特に対岸の斜面の高所に立つ人家が目を引く。新発地の集落と思う。 |
 |
対岸の高所にも人家が見られる
|
四国の、特に徳島や高知の県境付近は一段と山深い。その山沿いには、奥の方まで人家が点在し、ことに驚かされる。
こうした山間部に位置する集落は、ある意味四国の山深さを象徴する存在だ。
県道などの幹線路から分岐する細い道が急斜面を縦横に走り、その道沿いに石垣を築いて人家が立つ。その暮らしとはどんなんものだろうかと想像させられる。
さぞかし眺めはいいことだろう。それこそ自宅に「棧敷席」があるかのようだ。 |
 |
|
ただ、そうした人家の中には雨戸が閉じられ、既に人の気配がなくなったものも多く見掛ける。
こうした地での生活の困難さをうかがわせている。 多分下森清という集落の人家を後に、沿道には暫く人家を見ない。道は谷に沿って真南に位置する峠方向に狭い道を進む。 |
 道の様子 (撮影 2015. 5.28) 暫く人家を見ない |
 道の様子 (撮影 2015. 5.28) この先ヘアピンカーブ |
|
<新発地分岐> 下森清から1km程で、道は棧敷峠では少ないつづら折りの区間に差し掛かる。その最初のヘアピンカーブに分岐が一本ある。 看板が完備で、「新発地」、「町指定天然記念物 エドヒガン(桜)」などと案内がある。 その道は加茂谷川の対岸に渡り、新発地集落へと通じるようだ。 やや寂しい道に見えたが、地形図ではその沿道に意外な程多くの人家が点在することになっている。 |
 新発地への分岐 (撮影 2015. 5.28) エドヒガン桜が名所となっているようだが、 一般の道路地図などにはその記載は見当たらない |
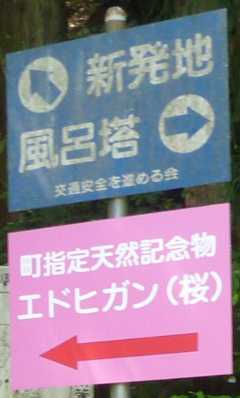 分岐に立つ看板 (撮影 2015. 5.28) |
| <つづら折り> つづら折りの区間は、比較的新しい舗装路で、ガードレールも完備とあって容易に通過できる。つづら折りを登り切ると、道は再び南の峠方向を向く。 高度を上げたので、視界が更に広がった(下の写真)。前方には峠がある山稜もそろそろ見えだす。 こちらの県道沿いにはまだ暫く人家を見ないが、対岸の山腹には新発地集落の人家を望む。 |
 |
 沿道の人家 (撮影 2015. 5.28) |
<奥森清の人家> 右手に鋭角に上る道を分ける。地図を見るとそちらに奥森清の集落があるようだ。また、県道沿いにも人家が少し現れる(左の写真)。 東みよし町側の県道沿いに立つ人家としては、最奥になるのではないだろうか。車道より一段高い所に大きな屋根の母屋を構える。 ただ、雨戸は全て閉じられ、人が定住する様子はなかった。 |
|
<奥森清の先> 沿道に人家やその形跡などは全く見られなくなった。すると道路の右脇に小さな滝となって流れ落ちる沢が目に留まった(右の写真)。 この付近ではもう加茂谷川にもはっきりとした本流としての流れは見られず、こうした小さな支流に分かれている。 丁度路肩に目にしたその沢も、棧敷峠方向から流れ下る源流の一つと言える。 滝を過ぎると峠のある山稜を前に、道は大きな蛇行を開始する。谷筋に通じる道から、稜線の北斜面をよじ登る道に変わるのだ。 峠までおよそ4kmの道程、高度差で約400mを残す。平均1/10の勾配と険しい。 |
 峠方向から流れ下る小さな滝 (撮影 2015. 5.28) これも加茂谷川の源流の一つ |
 道の様子 (撮影 2015. 5.28) |
<道の様子> 人家は途切れたが、県道からはまだ時折右に左にと分岐が見られる。また、軽トラックや軽自動車などともすれ違う。 県道からは見られないが、近くに人家が立つのかもしれない。 道は狭いながらも整備は行き届き、険しさは感じない。ただ、木々に囲まれ視界はほとんど広がらないのは残念だ。 <工事個所> 鋭いカーブを一つ曲がると、道は一転真西を目指す。稜線にほぼ並行することになる。これまで道の左手になっていた谷が、右手に移る。 すると工事個所を通過した。治山ダムの工事のようであった。砂を積んだダンプも通る。 |
 工事個所 (撮影 2015. 5.28) 工事看板には治山ダム工事とあった |
 工事個所を過ぎる (撮影 2015. 5.28) 大きなクレーンが立ち、架線作業中とあった |
|
道は2km近くも西へ向かう。峠の峰を目の前に大きな蛇行である。これはやはり棧敷峠に車道を開削した時のコースであろうか。
歩いて峠を越えていた時代は、もっと短い距離で峠に達していたのではないだろうかと思わされる。
ただ、現在の地形図には点線表記の徒歩道など、旧道の手掛かりとなる道は全く描かれていない。 |
 県道標識が立つ (撮影 2015. 5.28) この区間は旧道ではないのかも |
 県道標識 (撮影 2015. 5.28) 地名は「奥森清」とある |
|
<宮本林道> 途中、林道宮本線が右の麓方向へ分岐する。加茂谷川本流の谷と西側の支流との間の尾根上を森清集落方面へと下るようだ。 <旧西祖谷村への道を分岐> 道は西側支流との分水界を少し越えた所まで来て、やっと東へと引き返す。そのカーブから更に西へと延びる林道が分岐する(下の写真)。 入口を入って直ぐに小さな小屋が立つ。林道名を示す看板などはなかったようだ。その道は、旧西祖谷山村との境を越え、松尾川ダムへと通じているらしい。 古い道路地図では町村境は越えていたが、松尾川ダムに至る途中で途切れていた道だ。地形図では今も車道の一部が描かれていない。 |
 旧西祖谷山村へと続く道が前方へ分岐 (撮影 2015. 5.28) 本線はここで左急カーブ |
 分岐する道を見る (撮影 2015. 5.28) 右手に小屋が立つ |
|
加茂谷川水域(西側支流)と松尾川水域の分水界を越えるその道は、地形的には棧敷峠に並ぶ峠道だが、道路地図や地形図などに峠名などの記載はない。
古くから道が通じていた可能性もあるが、あまり利用価値の高い峠ではなかったのかもしれない。 |
| 東へと峠に向かう |
|
<道は東へ> 西に大きくそれた分、道は東へ戻りだす。峠まで約1.5kmを残す。右手から徐々に三好市との境を成す峰が迫って来る。 左手には加茂谷川本流の谷が鋭く落ち込んでいる。 <地蔵> 林が途切れ谷間の景色が少し広がった所で、道の反対側のコンクリート壁に埋め込まれて一体の地蔵が佇んでいた。 建立日は「寛政五丑年」と刻まれている。寛政五年とは西暦で1793年になり、この時は丑(うし)年だったようだ。 江戸時代も末期に当たり、明治維新まで後70年程である。 この地蔵建立は当然ながら今の車道が開削されるずっと前のことで、こうした古い地蔵がこの地に残されているということは、やはり この道が古くからの棧敷峠の道であることを示しているのだろう。ただ、地蔵が何らかの事情で他の場所からここへ移られて来た可能性は残る。 |
 コンクリート壁に小さな祠 (撮影 2015. 5.28) |
 地蔵 (撮影 2015. 5.28) |
 左手に谷が開けて来る (撮影 2015. 5.28) 道は真っ直ぐ峠に向かう |
<視界が開ける> 道は加茂谷川の谷の真正面に躍り出ようとしている。道の左手に視界が広がりだす。その景色に目移りするが、焦ることはない。 この先に絶好の場所が待っている。 <展望所> 峠から7、800m手前、谷に張り出して路肩にちょっとした広場がある。その箇所だけガードレールがなく、車を乗り入れることができる。 広場の周囲の樹木は切り払われていて、何の看板もないが、ここは展望所として整えられているようだ。 |
 展望所 (撮影 2015. 5.28) 峠方向に見る |
 展望所 (撮影 2015. 5.28) 麓方向に見る |
|
<展望所からの景色> アクセントのようにして立つ裸の一本の木の幹が残され、その向こうに加茂谷川の谷が下る。 谷の間からは吉野川の流れる麓が僅かにのぞき、三角州のような旧三加茂町の市街地が遠望される。 彼方には徳島・香川の県境ともなる讃岐(さぬき)山脈が空との境を成して連なる。丁度正面にそびえるややとがった山は大川山(1043m)であろうか。 讃岐山脈中、第二の高峰のようだ。 その山の西、約5、6kmには東山峠が稜線を越え、香川県の塩入へと通じる筈だ。 下の写真の左端の鞍部がそうかもしれない。 |
 |
| <新しい棧敷席> 現在の棧敷峠は木々が生い茂り、残念ながら峠からの景色は望めない。眺めるものがない棧敷峠ではしょうがない。 そこで、峠の手前にあるこの展望所は、その代用として新しく設けられたのではないだろうか。棧敷峠の新しい棧敷席という訳だ。 駐車ペースもあり、車で立寄るには都合がよくなった。 ただ、峠より7、800m程西に寄ってる為、加茂谷川の谷筋の正面からは少し外れている気がする。 古くから峠より眺められた景色とは、ちょっと異なるのであった。 |
 以前の棧敷峠からの景色(再掲) (撮影 1993. 5. 3) 現在はもうこの視界は得られない |
|
<旧三加茂町市街を遠望> 市街を望遠レンズで撮ると、左右方向に直線的に吉野川が流れ、そこい蛇行しながら加茂谷川が注ぐ様子がうかがえる。 吉野川に注ぐ少し手前の右岸に、茶色く見える大きな敷地があるが、多分三加茂中学校の校庭であろう。 手前左側の山の中腹に開けた土地が見え、人家が多く点在するのが分かる。県道沿いからは確認できなかったが加茂山集落のようだ。 山中に大きな生活空間が広がるのに驚かされる。 |
 |
 鉄塔脇を過ぎる (撮影 2015. 5.28) |
<ラストラン> 展望所を過ぎると峠へのラストランである。視界はあまりない。途中、一本の鉄塔が目に付いた。この付近に大きな送電線はなく、多分電波塔か何かであろう。 先端は稜線の上を越えてそびえているのかもしれない。 ここに至っても、軽トラが追い越して行ったり、軽ワゴンが峠方向から下って来たりと、僅かながら行き交う車に出合う。 道は緩い蛇行を繰り返しながら淡々と上る。いよいよ右手から三好市との境を成す稜線が近付いて来る。 |
| 峠の東みよし町側 |
| <分岐の看板> 棧敷峠は峠の切通しは最後の最後まで見えて来ない。代わりに分岐を示す道路看板が迎えてくれる。 直進は「水の丸」、右折が県道44号の続きで深渕」とある。 |
 前方に分岐を示す道路看板 (撮影 2015. 5.28) |
 道路看板 (撮影 2015. 5.28) |
|
<三叉路> 棧敷峠はなかなか見事な切通しで、峠の形そのものは良いのだが、残念ながら道の繋がりが美しくない。 峠から道が分岐することは時々あることだが、棧敷峠の場合は完全なT字路になっている。 三好市側から東みよし町へと切通しを抜けると、その正面が直ぐに行止りで、道が左右に分かれるのだ。 峠の東みよし町側の崖が鋭く切れ落ちているので、どうしてもこうした道の付け方になってしまうのだろうが、 東みよし町から峠に登って来た時の味わいは今一つである。 |
 峠の三叉路 (撮影 2015. 5.28) 右に曲がると峠の切通し |
 看板など (撮影 2015. 5.28) |
<分岐に立つ看板> 峠の東みよし町側は三叉路になっていることもあって、看板などがいろいろと立つ。 「風呂塔キャンプ場 3km」とある木製の矢印看板は、22年前に訪れた時にあった物と同じに見える。 それ以外に風呂塔キャンプ場方向には、 風呂塔キャンプ場 3km 四国の軽井沢 水の丸パイロット5.1km 風呂塔キャンプ場 3K 水の丸ふれあい公園 3K 六 地 蔵 4K ゆめりあ34 6K などと看板にある。「パイロット」とあるのは、高冷地野菜のパイロット農場のことと思われる。 「六地蔵」とは老松の下に六地蔵が祀られるという六地蔵峠のことだろう。 |
| 峠の切通し |

|
東みよし町側より見る
 切通しの中より東みよし町側を見る (撮影 2015. 5.28) 今は視界がない |
<峠の切通し> 立ち並ぶ看板を過ぎ、崖を背にして三叉路に立つと、やっと棧敷峠の狭い切通しがのぞける(上の写真)。間口も狭く、道はほぼ直角に曲がって行く。 切通しは特にこちらの東みよし町側の方が暗い感じだ。ほとんどトンネルの中に入って行くようである。 以前は、切通しを東みよし町(旧三加茂町)側に抜けると目の前に視界が広がった。古いツーリングマップ(ル)にも、 「吉野川がそこに見えるが実際にはそれ以上時間がかかる」と峠の部分にコメントが書かれていた。 しかし、今は木々が成長してしまっている。「東みよし町」の看板ばかりが新しい。 |
|
<風呂塔キャンプ場への道> 狭いながらも意外としっかりした道が峠より東へと延びている。 通ったことはないが、地図で見ると、風呂塔キャンプ場以外にも、北へ派生する尾根上を六地蔵峠方面へと分かれて進んでいる。 六地蔵峠は山口谷川と大藤谷川の分水界に位置する。 大藤谷川寄りに奥村という集落が見られ、そこを通って麓まで車で降りられる可能性がある。 |
 峠より風呂塔キャンプ場への道を見る (撮影 2015. 5.28) 右手に古い看板 |
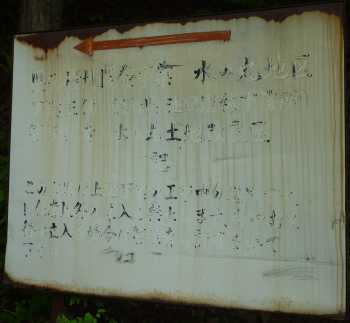 古い看板 (撮影 2015. 5.28) |
<古い看板> 風呂塔キャンプ場への道の脇に古い看板が立つ。キャンプ場などの案内看板かと思ったら、 よく見ると「県営農地開発事業 水の丸地区」とあった。 この道路はその事業の工事中の道路で、関係者以外立ち入り禁止と書かれている。 <四国の軽井沢> 今は風呂塔キャンプ場へ行く為、誰でも通ってよさそうな道である。 三加茂は「四国の軽井沢」の別名を持つそうで、そのキャンプ場や農園を一目見ておきたかった。 |
 |
この左が峠の切通し
|
<市街地方向への看板> 風呂塔キャンプ場方面から峠を見ても、ちゃんと案内看板が立つ。 左の棧敷峠を抜ける方向に「落合峠 12K」、 直進の麓方向に「東みよし町役場13K 加茂農村公園13K」とある。 「東みよし」の部分は書き換えられていて、比較的最近手直しされていることが分かる。 これ程しっかり看板を立てるのは、奥村集落方面からも車で登って来れる証拠かとも思った。 |
 峠手前の看板 (撮影 2015. 5.28) |
 峠より三加茂町市街方向を見る (撮影 2015. 5.28) 道路看板の県道44方向には「加茂」とのみある |
 三加茂市街方向の道 (撮影 2015. 5.28) 右手の標柱には「屋外広告物 禁止地域」とある |
| 切通しを三好市側へ |
 |
三好市方向に見る
 切通し途中 (撮影 2015. 5.28) 三好市方向に見る |
<切通しを三好市側へ> 棧敷峠の切通しは長く感じる。狭く暗い。途中、頭上を覆う木々の隙間から僅かに日差しが射し込む。 道の起伏もあり、三好市方向に向けてやや右にカーブして下る。 <標高> 文献(角川日本地名大辞典)では、棧敷峠の標高を1,021mとしている。現在の地形図では1,020mと1,030mの間で、それからすると1,021mは妥当な値だ。 切通しの途中にある道の最高所は、実際はもう少し高いのではないかとも思う。 尚、「日本百名峠」では峠の標高を1,056mと記している。大きく数値が異なる。 現在は山稜に車道を通して、深い切通しになっているが、古い棧敷峠はもっと峰の高い位置に通じていたことと思う。 それでも切通しの深さはせいぜい10mで、これ程の違いは説明できない。 |
| <峠の三好市側> 切通しからのぞく三好市側は、日差しが射し込み急に明るくなっている。峠の切通しはほぼ南北方向に通じ、三好市側は太陽が当たり易い南側に位置する。 |
 県道標識など (撮影 2015. 5.28) 「三好市東祖谷」とある |
 峠の三好市側 (撮影 2015. 5.28) 切通しより見る |
| <三好市側の広場> 三好市側が明るいのは、山稜の南に位置するという理由だけでなく、切通しを抜けた先にちょっとした広場があるからだ。但し、何の見晴らしもない。 広場の周囲はぐるりと高い木々が囲んでいる。上空だけがポッカリと開け、広場の土の地面に太陽光が降り注いでいる。 ちょっと変わった空間となっている。この場所は、初めて来た時にも既にあったようで、かすかに印象に残っている。 野宿地として使えそうだと思ったようだ。 |
 三好市側から切通しを見る (撮影 2015. 5.28) 写真の右端から稜線に登る登山道が始まっている |
 三好市側にある広場 (撮影 2015. 5.28) 明るい陽射しがここだけに射し込む |
| <登山道> 広場からは、峠の暗い切通しと、深淵方面へと下る2筋の車道が通じるだけだ。広場の周辺には少しゴミが散らかっているのが目に付く。 何かの作業場所とも考えたが、やはり登山用の駐車場として使われるのだろう。 広場の片隅に稜線上に登る登山道が始まっていて、稜線沿いにキャンプ場もある風呂塔へと山道が続いているようだ。 ただ、登山口には何の案内看板もなく、道も踏み跡程度のものである。 |
 |
この左手が広場
|
<峠の感想(余談)> 初めてこの棧敷峠を訪れた時は、多分ジムニーから降りることもなく、写真一枚を撮って旧三加茂町へと下って行った。 今回は峠の切通しも2往復くらい歩いては、じっくり峠を噛み締めたのであった。 歩くと切通しは尚更長く感じられる。写真も何枚も撮った。写真の撮りようによっては、面白そうな切通しに見える。 まあまあ味わいがあると言っていいのではないだろうか。ただ、峠全体としては、やはり東みよし町側のT字路はいただけない。 折角の眺望もなくなってしまい、あまりいいところがない。 |
 三好市側より切通しを見る (撮影 2015. 5.28) |
 稜線の上に何か建物が見える (撮影 2015. 5.28) |
<稜線上に建物> 切通しを見上げながら歩いていると、木々の間から何か建物のような物が見える。 古い棧敷峠はこの稜線の上にあったのだろうから、それに関する記念碑などがあるのかもしれないと思わされた。 |
|
<稜線上へ> 車での旅をモットーとしているので、旅の途中であまり登山めいたことはしないことにしている。そうした服装や装備も持ち合わせていない。ただ、今回は10m程の稜線へ登るだけである。それで棧敷峠の歴史に少しでも触れられれば、こんな嬉しいことはない。 |
 稜線上へ登る道 (撮影 2015. 5.28) |
 つづら折りを登る (撮影 2015. 5.28) 左下が広場、右上が稜線上へ |
妻を広場に残し、山道を歩き始めた。少しのつづら折りで稜線上へと至る。 <休憩所> すると、意外に立派で頑丈そうなコンクリート造りの建造物が、生い茂った木々の中に立っていた。朽ちた様子はない。中央には椅子やテーブルがある。 どう見ても、休憩所だった。蜘蛛の巣を掻き分け、周囲を歩き回るが、旧棧敷峠を示すような痕跡は全く見付からない。 私が降りて来るのが遅いと思ったのか、妻もやって来て一緒に調べるが、やはり休憩所という判断である。 |
 休憩所 (撮影 2015. 5.28) |
 休憩所 (撮影 2015. 5.28) |
|
多分、風呂塔キャンプ場などの建設の一環として、ここにこうした立派な休憩所を設けたのではないだろうか。
建設当時はこの場所からも旧三加茂町側に景色が広がったことだろう。
今は休憩所の建物の周囲にも草木が生い茂り、休憩するだけでも、あまり気持ちがいい場所とは言えない。 |
| 三好市側へ下る |
|
<三好市> 棧敷峠の南側は現在は三好市となる。JR徳島線の阿波池田駅がある吉野川沿いの旧池田町までも、三好市となっている。 吉野川沿いの東みよし町から峠を越えても、相変わらず吉野川沿いにも市域を広げる三好市では、ちょっと変な感じである。 やはり昔のように「東祖谷山村」といった方が、峠を越えて山の中に入って来たという感じがする。 住所は、看板にもあったが、「三好市東祖谷」で、更に詳しくは「落合」と呼ぶことになる。 ただ、落合の中心地は、この先落合峠を越えたずっと向こうの祖谷川沿いになる。 <三好市側に下る> 峠を三好市側に下る道は、一路西を向く。右手に山稜を見上げる。東みよし町側と比べると、比較的穏やかな地形だ。道もゆったり下る。 |
 |
|
<小さな箱(余談)> 今回の四国の旅では、峠道の傍らに小さな箱状の物が置かれているのをよく目にした。一つの峠道に間隔を置いて複数個置かれていたこともある。 別に峠道に限ったことではなく、山間部に通じる道にあったと言うべきだろう。徳島県や高知県の山深い地で見掛けた。 その箱は、大抵は木製で、高さ30cm程だ。周囲に窓などは開いていない。ただ、屋根の部分にトタン板などを被せ、その上に重しとなる石を乗せている。 これまで四国は何度も旅をしてきているが、こうした物体には気が付いたことはない。多分、最近になってから置かれ始めた物だろう。 この棧敷峠でも、三好市側に下り始めて間もなく、擁壁の上に例の箱が一つあるのを目にした。中に何が入っているのだろうかと気に掛かる。 坂道によくある滑り止めの砂や凍結防止剤かとも思ったが、それにしては箱が小さ過ぎる。 トタン板を外して中をのぞく訳にもいかず、結局今もって謎のままである。 |
 擁壁の上に小さな箱が置かれている (撮影 2015. 5.28) |
 |
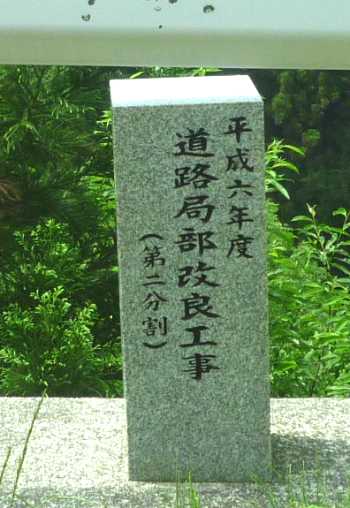 道の改修工事の標柱 (撮影 2015. 5.28) |
<道の様子> 道は部分的に広く、路面のアスファルトの状態も良好だ。 「平成六年度 道路局部改修工事(第二分割)」と書かれた小さな標柱がガードレールの下にポツンと立っていた。 20年程前に改修工事が行われたようである。周辺の擁壁などもまだまだ新しそうに見えた。私が初めて越えたのは、その改修前であったろうか。 もう、全く記憶にない。 <稜線へと登る道> 右手の稜線に沿って数100m下ると、左急カーブに差し掛かる手前から、右手に登る車道が分岐する(下の写真)。 直ぐにゲートで通行止になっているが、道路地図によっては、東みよし町との境となる稜線の上までも道が続いているようだ。 地形図の等高線を読むと、稜線上の1056mのちょっとしたピークを挟んで、棧敷峠から西へ400m程離れた位置に同じような鞍部がある。 道はそこまで登っているようだ(地形図には道の記載はない)。その鞍部の標高は1020m〜1030mで、棧敷峠とほとんど変わらない。 |
|
ここで疑惑が湧く。わざわざ現在の棧敷峠の位置まで東に移動することなく、この鞍部を越えた方が峠道としてはずっと近道だ。
東みよし町側の地形がやや急峻で、車道を通すには現在の峠の方が好ましいかもしれないが、人が歩いて越える峠なら、少しばかりの険しさより、
道程が短い方がいい筈である。 実は東みよし町側を峠に向けて走っていた時、稜線がもう手に届くような距離にあったので、そこに登る道があるのではないかと注意していた。 しかし、結局はそれらしき道は確認できなかった。古い棧敷峠がもっと他の場所にあったのではないかというのは、単なる憶測に過ぎないようだった。 |
 正面右に道が分岐 (撮影 2015. 5.28) |
 |
左手上方が峠方向
 右手に細い道が分岐 (撮影 2015. 5.28) こちらが旧道? |
<つづら折り> 稜線へ登る道を分けて以降、本線は2度のヘアピンカーブを曲がる大きなつづら折り区間になる。 三好市側の道は全般的に地味だが、この区間だけはやや豪快な峠道の様相を示している。 <ショートカットの道> 最初のカーブを曲がり終わった所で、ほとんど気付き難いが、細い道が右下に分かれる。 地図によっては、つづら折りをショートカットする様に道が描かれている(こちらも地形図にはない道)。 現在の大きなS字カーブの道は、どう考えても車道として開削した道に思える。古くからの峠道は、その谷筋に通じる細い山道の方ではないだろうか。 ただ、既に歩くことも難しそうな道になっている。 |
|
<旧道?> 考えてみると、一つのヘアピンカーブの前後で道が分岐していることになる。一つは稜線上の鞍部に登り、一つはその鞍部に続く谷筋に下る。 これらは元は一筋の道であったようにも思える。 するとまた、棧敷峠に旧峠があったのではないかという考えが浮かんで来るのだが、やはり考え過ぎだろう。 |
| 山小屋以降 |
 左手に山小屋 (撮影 2015. 5.28) |
<山小屋> S字のつづら折りがもう終ろうとする所に、山小屋が一軒立っている。 外壁に「登山についての心得」とあるので、山小屋であることが分かる。比較的大きな建屋で、宿泊もできたのかもしれない。 ただ、もう老朽化し、あまり使われているような形跡はない。 |
 山小屋 (撮影 2015. 5.28) |
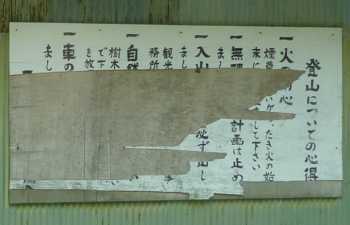 山小屋の看板 (撮影 2015. 5.28) |
|
山小屋の周囲には他にも家屋が見られるが、こちらも使われている様子はうかがえない。
何の記念か確認はしなかったが、小屋の近くには石碑なども立っている。 |
 |
|
<谷沿いに> つづら折り区間を終えると、棧敷峠から下る谷と、もう一つ西にある鞍部から下る谷とが合わさった谷沿いを道が行くようになる。 この入口付近の右手より、最初のヘアピンカーブ後から分かれて下る山道が合流している筈だが、それらしい道の痕跡ははっきりとは見られない。 |
 谷沿いの道に (撮影 2015. 5.28) 前方の一段高い所に柵が張り巡らされ、 家畜小屋らしき建物がある 右端に主要地方道の看板が立つ |
 主要地方道の看板 (撮影 2015. 5.28) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |
<主要地方道の看板> 代わりに、その付近に一つの看板が立っている。「主要地方道 三加茂東祖谷山線 深渕工区 完成予想図」と題している。 「平成六年度 道路局部改修工事」と関係するものだろうか。ならば、既に完成していることになる。 看板の図(下の写真)では、進行方向右手に牛と思われる放牧場の様子が描かれ、その一角に家畜小屋が立つ。 左手には川が寄り添って流れ、車道から少し下った所に一軒の家屋が見られる。 実際の周囲の様子も正にその通りだった。ただ、草を食む牛たちの姿はなく、左側に立つ家屋は使われなくなってから久しい様子だ。 路面よりその家屋の敷地が少し低いのは、道が改修される前からあった家屋だからかもしれない。 以前の峠道は家屋と同じ高さに通じていたのだろう。 |
 |
 左手に家屋 (撮影 2015. 5.28) |
 家屋の様子 (撮影 2015. 5.28)
|
|
<二車線路> 家屋を過ぎると、道はセンターラインが引かれた二車線路に変わる。 東みよし町の新田神社の先で途切れたセンターラインだったが、峠を越えたここでやっと復活である。 これも平成6年度前後の改修工事によるものだろう。 <松尾川支流沿い> 道は棧敷峠付近を源流とする細い川の右岸に通じる。松尾川の支流となるが、この川の名前は不明だ。 地形図には川自体が描かれていない。 |
 センターラインのある道 (撮影 2015. 5.28) |
 この先でセンターラインが途切れる (撮影 2015. 5.28) |
<川沿いの道> 改修後の車道は川からやや離れた高みに通じる。途中、川の方へ降りる道の分岐があったが、ゲートで通行止だった。 そちらに旧道が残っているのかもしれない。 <狭路に> 快適な二車線路も僅か400m程で、また狭い道に戻る。この先、落合峠を越えた祖谷川沿いまで、センターラインにはお目に掛かれない。 いや、秘境として名高い祖谷川沿いになったとて、滅多に二車線路は出て来ないのだが。 |
|
<道の様子>
狭い道に戻ってからは、川に沿ったやや屈曲する道となる。細々と流れる川面を左手に見る。木々に囲まれ、視界の狭い道だ。 <対岸に道> よく見ると、林の間から対岸にも道が通じるのが見えた。林業などの作業道であろうか。 |
 道の様子 (撮影 2015. 5.28) |
 この先、橋を渡って左岸へ (撮影 2015. 5.28) 橋の手前を右に道が分岐していたらしい |
<左岸へ>
暫く行くと、本線も小さな橋で左岸へと渡る。橋の手前に多分「1.6」と書かれた道路標識が立っている。 橋の重量制限1.6tを示しているのだろうが、随分古ぼけている。 <貯水池右岸沿いの道> 橋の先はこれまでの川の左岸であるが、そろそろ松尾川ダムの貯水池の上流部に差し掛かっている。 後で分かったことだが、その貯水池の右岸沿いにも道が通じていて、ダム堰堤にまで至るようだ。 どうやら橋の重量制限を示す道路標識の直ぐ後ろから、その道が分岐していたらしい。勿論、車が通れるような道ではないが。 |
| 峠道の終点へ |
| <松尾川ダム貯水池> 川の左岸沿いになると、間もなく右手の川幅が広がってくる。松尾川本流を堰き止めてできた松尾川ダム貯水池だ。 松尾川ダムは文献などでは「春ノ木尾ダム」とも書かれていた。 「春ノ木尾」とは旧西祖谷山村に見える地名だ。一方、ダムの上流部は旧東祖谷山村になる。そこに深淵の地名がある。 |
 |
| <松尾川本流> 松尾川本流は貯水池から上流部を深淵川(深渕川)と名を変える。南の落合峠を源としているとのこと。 よって北の棧敷峠から流れ下る川は支流となる。ただ、松尾川ダム湖は、これら南北それぞれから流れて来た2筋の川が合わさってできたような形をしている。 |
 峠道の終点付近 (撮影 2015. 5.28) |
<峠道の終点へ> 棧敷峠から落合峠へと続く県道44号は、貯水池の東岸に沿う。支流沿いからいつしか本流沿いに移って行く。 本流沿いになると、地形的にはこれはもう落合峠の道と言わざるを得ない。棧敷峠の道は支流沿いまでである。 しかし、川ではなく広い貯水池となってしまっているので、はっきりした道の終着点がないのだ。 地図を見ると、道が西の貯水池側に張り出した辺りが、支流から本流へと転換する場所である。 そこで道は左へとカーブする(左の写真)。峠道の終着点としては、何ともアバウトな地点である。 |
|
<深淵へ> 地形的には、棧敷峠の道は貯水池の右岸沿いにダム下流の松尾川本流方向へと下るべきである。 しかし、そちらには山道しか通じず、車で行くことはできない。また、この棧敷峠は落合峠と共に祖谷川沿いの落合集落へと通じる祖谷街道である 2つの峠道を繋ぎ合わせて考えるしかないようだ。 深淵川沿いとなる貯水池東岸を更に進むと、建屋が現れ出す。整備されたトイレも見掛けた。その先に深淵の家屋が現れてくる。 道も深淵集落へ向けてやや下る。深淵は、吉野川沿いの三加茂市街地と祖谷川沿いの落合集落との間にある中継地点である。 そこが棧敷峠の終着点としてもいいのかもしれないが、集落の詳しいことは、落合峠を再掲載した時に譲ることとしたい。 |
 右手にトイレ (撮影 2015. 5.28) この先に深淵の集落がある |
| |
|
これまで峠の部分だけに限られていた棧敷峠のイメージが、今回の旅で峠道全体に広がった。
東みよし町側の道程は14km程と走り応えがあり、阿波加茂駅周辺の市街地に始まり、加茂谷川沿いの集落、山腹に点在する人家、
つづら折りを登った先の展望所からの眺めと、変化に富む楽しいものであった。 三好市側は距離も2、3kmと短く、やや尻切れトンボの感はぬぐえないが、ここと落合峠の峠道でしか辿り着けない長尾川ダム湖上流部や、 深淵川沿いにひっそり佇む深淵集落の様子は、祖谷川本流沿いではないまた別の秘境「祖谷」を思わせた。 全線舗装で山岳道路のような部分はなく、途中で軽トラともすれ違う峠道ではあるが、 その道の険しさ以上の険しさを感じさせられる、棧敷峠であった。 |
| |
| <走行日> ・1993. 5. 3 旧東祖谷山村→旧三加茂町 ジムニーにて ・2015. 5.28 東みよし町→三好市 パジェロ・ミニにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典のオンライン版(JLogos) ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、 こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2015 Copyright 蓑上誠一>
|
峠と旅 峠リスト
