| ホームページ★峠と旅★ |
愛染峠
あいぜんとうげ
(峠と旅 No.207)
朝日連峰の奥懐に分け入った林道の峠道
(初掲載 2013. 3.31 最終峠走行 2012.11. 7)
(初掲載 2013. 3.31 最終峠走行 2012.11. 7)
|
|
 |
愛染峠 (撮影
2012.11. 7)
手前は山形県西村山郡朝日町白倉
奥は同県西置賜郡白鷹町黒鴨
道は林道黒鴨線
峠の標高は約1,070m
(国土地理院の1/25,000地形図より読む)
峠の周辺全体が開けているので、峠道自体はあまり峠らしく見えない
手前は山形県西村山郡朝日町白倉
奥は同県西置賜郡白鷹町黒鴨
道は林道黒鴨線
峠の標高は約1,070m
(国土地理院の1/25,000地形図より読む)
峠の周辺全体が開けているので、峠道自体はあまり峠らしく見えない
| 初めに |
|
愛染峠は、一生訪れることができない峠のように思っていた。1994年の8月と翌年の同じく8月に朝日町側からアクセスするも、朝日鉱泉から先の林道が通
行止であった。この峠は東北地方の、それも非常に山深い地にあり、容易に旅ができる場所にはない。林道の通行止がいつ解除されるかも分らず、これでは愛染
峠と呼ぶ面白い名の峠を見る機会は、一生巡って来ないものと諦めていた。 それが去年(2012年)のこと、ほとんど期待せずに朝日鉱泉まで行ってみると、その先の道が開かれているではないか。これは運が良いとばかりに勇んで 峠まで進んだのだった。しかし、峠にゲートがあり、白鷹町には越えられなかった。それで、白鷹町側の峠道は全く未経験なのだが、愛染峠が見られたのが嬉し くて、早々とここに掲載させてもらうこととした。その為、このページでは白鷹町側に関しての情報は皆無なので、悪しからず。 |
| 峠の所在など |
|
この愛染峠を地図上で見付けるには、まず山形・新潟の県境にそびえる朝日連峰を探し、その朝日連峰の中の主峰である大朝日岳(おおあさひだけ、
1,870m)を確認し、その大朝日岳の東、
約6Km程に朝日鉱泉があるので、その鉱泉の近くを南北に通る道沿いを南に少し目を移すと、寂しそうな峠がポツンとある。それが愛染峠だ。 正確には山形県 の朝日町(あさひまち)と白鷹町(しらたかまち)の境に位置するのだが、そもそも他国者には朝日町や白鷹町と言われても、山形県のどの辺りにある町だか さっぱり分 らないのである。それで、上の様な探し方となる。 ところが考えてみると、朝日町にも白鷹町にもこれまで何度か旅をし、宿泊までしたことがあった。朝日町で は一般の旅館の二見屋さんに(1994. 8.18 泊)、白鷹町では公共の宿のパレス松風さんに(2003.12.24 泊)、それぞれお世話になっている。 旅先での宿はそれなりに記憶に残るもので、二見屋さんでは、多分その宿の娘さんと思われる若い女性に案内された。宿泊 客は丁度私一人であったようで、翌日の朝食は、その宿の家族の方と一緒のテーブルで食べたような記憶がある。パレス松風さんでは、体調を崩して食事も摂ら ず、部屋でダウンしていた覚えがある。それぞれに印象が残っているのだが、それでも朝日町や白鷹町の位置は、さっぱり覚えられない。それで今でも愛染峠を 見付ける時は、まず朝日 連峰を探すこととなるのであった。 |
| <余
談> 旅の宿は旅に於ける大きな要素で、旅での貴重な経験の一つだと思っている。それで、宿ではないのだが、「サラリーマン野宿旅」などと、旅先でテントなど で一夜を過ごすことにこだわったホームページを出したりした(現在、更新が滞っています)。この頃は、体力の衰えもあり、野宿はパッタリご無沙汰で、代わ りに一般の旅館に泊まってしまうことが多い。 今年、山梨県に引っ越して来たので、ここはひとつ、どこか県内の温泉地にでも一泊しようと企て、つい最近、下部(しもべ)温泉に行って来た。旧下部町の 下部川に沿って旅館が並ぶ古い温泉地だ。(その上流部には仮称:湯 之奥猪之頭峠がある)。旅館街の途中に神泉橋という橋が架かっていて、その橋の袂の旅館に宿泊した。 旅から帰り、そう言えばつげ義春さんも、その橋の近くの旅館に泊まったことを文章に書いていたと思い出し、「貧困旅行記」を確認してみると、偶然にも同じ 宿であった。つげ義春さんも、旅先の宿に関心があるようで、この他にもいろいろと文章にしている。 神泉橋の袂のその宿は、重厚な木造3階建ての昔ながらの旅館であった。ただ、名前が裕貴屋に変わっていた。つげ義春さんが泊まった頃は、大市館と呼ばれ てい たようだ。私達が泊まった部屋の備え付けのハンガーに、「大市館」と書かれてあるのを妻が見付けていた。以前の宿の名残であろう。 朝日町で二見屋さんに泊まったのは、宿泊情報(日本交通公社、1992年版)で偶然見付けたまでのことだったが、今にすると懐かしい思い出だ。ウェブで 少し調べてみたが、もうその宿は廃業しているようで、朝日町に二見屋と呼ぶ旅館は見付からない。 |
|
愛染峠の近くにある峠といえば、山形・新潟の県境に位置する蕨峠(わらび)や、同じく県境で朝日スーパー林道の峠(仮称:朝日峠)を思い出す。どちらも険しい林道の峠だ。愛染峠は県境を越える峠ではない
が、それらに劣らぬ険しい峠道である。 |
| 朝日町木川の分岐 |
| 当時、使いっていたツーリン
グマップ(東北 2輪車 1989年5月発行 昭文社)には、愛染峠の道は白鷹町側がまだ一本線で辛うじて記載される状態だった。肝心な峠の名前も書い
てない。通行止看板で愛染峠の名を知り、ここより更に山深い地にあるその峠を、いつの日か越えたいものだと思った。 |
 右がぶな峠を越える大規模林道 |
 |
 狭い県道が通じている |
|
木川の分岐の近く、ぶな峠の道沿いに、「大規模林道案内図」の看板が立つ(下の写真)。それには地蔵峠からぶな峠に至る林道が掲載されてい
る。また、国道287号沿いの宮宿方面から立木(たてき)、木川を通って白滝に至る県道も記載されている。県道の名前が白滝宮宿線と呼ばれることから、県
道終点はこ
の木川より更に上流に位置する白滝のようだ。 |
 右端に大規模林道案内図の看板が立つ |
 大規模林道案内図の看板 (撮影 2012.11. 7) (上の画像をクリックすると地図の拡大画像が表示されます) |
| 木川より峠を目指す |
 橋の手前右に、ぶな峠への旧道が分岐していた筈 |
木川の分岐より峠を目指す。ぶな峠を越える大規模林道とは打って変わって狭い県道だ。道は一旦朝日川の支流・大沢の川沿いに下り、古そうな橋で大沢を渡
る。 大規模林道が開通する以前は、その橋の袂を大沢の左岸に沿ってぶな峠を越える道が分岐していたようだ。1989年5月発行のツーリングマップには、そ の旧道が描かれている。今はその痕跡も定かでない。橋から振り返って見上げると、上に大規模林道のガードレールが見える。 天候は生憎の雨模様で、写真もうまく映らない。晴れていれば紅葉もきれいなことだろうに。 |
| 朝日川の左岸沿いに、寂しい県道が細々と続いて行く。未舗装と見間違うよう
な荒れたアスファルト路面である。 対岸の山の斜面に導水管が望められた(下の写真)。この上流に位置する朝日鉱泉の方から導かれた水で、発電を行っているようだ。間もなく左に分岐があ り、「朝日川第二発電所」とあった。その道は立入禁止である。 大沢を渡った後、何度も橋を渡る。朝日川には支流が多い。地図にない小さな沢が幾筋も朝日川に注いでいて、そのたびに橋を渡ることとなる。 |
 |
 |
 |
| 白滝 |
 右に分岐あり 左が本線 |
木川の分岐から3Km程で白滝に着く。かと言って、何がある訳ではない。Y
字を右
に荒れた未舗装路が分岐し、専用林道と書かれた看板が立つ。伐採作業中で立入禁止ともある。この道は朝日川の支流・白滝沢の左岸方向へと登って行く
ようだ。この後、朝日鉱泉前の駐車場で見掛けた「水源かん養保安林」の看板には、「白滝支線」と記されていた。 |
 |
白滝沢が朝日川に合流する付近は、谷がやや開け、車道からも川面が見渡せ る。晴天なら周囲の紅葉が美しかっただろうと思われる景色が広がった。 |
| 西五百川林道 |
| 白滝で県道289号・白滝宮宿線は終りとなる筈だが、それを示す物はない。
そもそもこの辺りに県道標識など皆無である。しかし、どこまでが県道でどこから林道だか、あまり意味がない。ずっと林道のようなものなのだ。 それでも、白滝沢に架 かる橋を渡った先で、林道標柱が一本立っていた(右の写真)。「西五百川林道」(にしいもがわりんどう)とある。白滝からこの上流3Km程にある朝日鉱泉 までが、そう呼ばれる林道だった思う。更に朝日鉱泉から愛染峠を越えて白鷹町に通じる林道が黒鴨林道だと記憶する。 |
 |
 |
路面はほとんど未舗装に近い部分も出てきた。「木材運搬車横断中」とか「伐
採作業中 通行注意」といった看板が目立つようになる。道が狭いので、こんな所で木材を積んだ大型トラックと鉢合せになると、非常に厄介だ。 過去に何度か 大変な思いをしたことがある。よくこんな狭い道をあんな大きなトラックが通れるものだと驚かされる。乗用車同士のように容易には離合できない。相手は大き いしそれに仕事だから、小さい遊びのこちらの車が対応することとなる。随分と長い距離をバックし、崖際のギリギリに車を寄せたこともあった。ただただト ラックが 現れないことを祈るばかりだ。 |
 |
 舗装が新しい |
|
道は相変わらず朝日川の左岸を南へ向けて進む。ほとんど未舗装状態だと思うと、今度は白線の白色も鮮やかな舗装路になったり、また橋を渡り、路肩に木材が
積まれてい
たりと、道に変化がある。 |
 地図にはこうした支流の川の名前など載っていない |
 |
| ただ、険しい地形に築かれた道であることだけは確かで、時々崖にへばり付く
ような道の箇所を過ぎる(右の写真)。山側は垂直にそそり立つコンクリートで法面が覆われ、谷側はガードレールもなく直ぐに朝日川に切れ落ちていたりす
る。油断禁
物である。 それでも、今回は木材運搬のトラックに一度も出くわさずに済んだのは良かった。峠からの帰りに一度、黄色の回転灯を点けたパトロール車とすれ違っただけ である。 |
 峠からの帰りに撮影 |
| 朝日川の右岸に渡る |
| 鳥獣保護区の看板を過ぎる
と、間もなく道は朝日川の本流を渡る。この先にある朝日鉱泉の手前800mくらいの地点だ。立木橋以降、ずっと左岸沿いだった道が、ここで右岸に渡り返
す。橋の欄干はとても低く、勢い余れば車は簡単に落ちそうである。如何にも古そうな橋だ。この付近は朝日川の谷が更に狭まり、ほとんど見通しが利かない。樹木に覆われ
た狭苦しい谷間に橋が一本渡っている。 |
 |
 |
右岸に渡っても道は相変わら
ず狭い。朝日川の方へ下る道が分岐していた(左下の写真)。朝日川第二発電所の取水口へ続く道らしい。関係者以外立入禁止である。
これまでずっと川に沿って進んで来た道が、少し川筋を離れて山腹を登るようになる(右下の写真)。僅かな九十九折りでやや高度を稼ぐ。一時、朝日川の流 れを感じること なく、紅葉の木々に包まれる。ここでも伐採された木材が路肩に積まれていたりする。支流の沢を一つ詰める。ノヅクラ沢と呼ばれる沢だと思う。 |
 |
 一時的に下流方向に進む |
| 朝日鉱泉 |
|
右手の川側に比較的大きな建物が見えて来る。2棟ほど建っている。朝日鉱泉だ。そちらの敷地に下る道がある。そこを過ぎると路肩に駐車スペースがある。こ
こで一休みできる。ただ、登山が盛んな季節には、登山客の車でいっぱいの時もあるようだ。 |
 |
 下流方向に見る ここを左に下る道がある |
|
木川の分岐以降、これといって車を停める適当な場所もなかったので、ここで大
休止とする。近くに建物があるというだけで、人は居ないかもしれないが、何となく安心感がある。いつもの様にお湯を沸かしてカップめんの昼食だ。また、周
囲を散策し、そこに立つ看板などを見て回る。ただ、駐車場の周囲は林に囲まれ、あまり遠望などはない。 |
 峠方向に見る 幾つかの看板が並ぶ |
 自然環境保全地域の看板 (撮影 2012.11. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |
 水源かん養保安林の看板 (撮影 2012.11. 7) (上の画像をクリックすると地図の拡大画像が表示されます) |
 |
| ところで1994年に来た時、通行止の看板に「朝日鉱泉 ナチュラリストの家」とあったが、その頃使っていた宿泊情報(JTB発行)にも朝日町の項にそ のナチュラリストの家が載っていた。れっきとした宿泊施設なのであった。今回は 冬期休業中なのか、ひと気がないようだ。 尚、ツーリングマップ(ル)などでは、朝日鉱泉の位置が、車道から見えている建物ではなく、ここより西のもう少し朝日川の上流部に示されている。そちら が鉱 泉の源泉が湧いている箇所なのだろうか。 |
 下流方向に見る |
| 1995年に再び愛染峠をトライした時は、この朝日鉱泉の前までやって来た
(下の写真)。しかし、その先は通行止で、車が進める状態ではなかった。通行止の看板には土砂崩壊のためとあった。仕方がないので、近くに立つ朝日連峰案
内図の看板などを写真に撮り、さっさと引き返すこととした。登山客の物と思われる車があふれていて、ジムニーを反転させるのに苦労した覚えがある。 |
 ロープと車が立ちふさがる |
 以前、駐車場にあったもの |
| その時写した「国立公園朝日連峰案内図」の写真を改めてよく見ると、峠の部分
に「黒鴨林道 愛染峠展望台」と書かれてあるのが辛うじて分かる(下の写真)。また、白滝には「白滝バス停」とあり、かつてはバスが通じていたようだ。こ
こでも朝日鉱泉の温泉マークが川の上流部に記されている。 |
 国立公園朝日連峰案内図 (撮影 1995. 8.17) 以前、駐車場にあったもの (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |
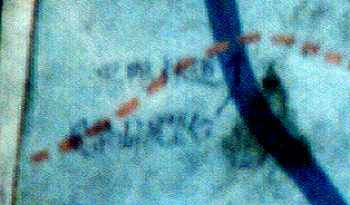 黒鴨林道と愛染峠展望台の文字 (撮影 1995. 8.17) この看板は現在はもうなく、 この頃では「愛染峠」と書かれた看板は見られない |
| 朝日鉱泉以降 |
| 朝日鉱泉を後に峠を目指す。とにかく今回は通行止の看板がないのが嬉しい。
これまでずっと諦めていた愛染峠が越えられるかもしれない。期待が高まる。 暫く川の右岸沿いの狭い道が続く。しかし、この 川はもう朝日川ではない。支流のヌルマタ沢である。「ヌ ルマタ沢・野川自然環境保全地域」という看板があっ たし、また「水源かん養保安林」の看板に書かれた地図に、その沢が示されている。ヌルマタ沢は南に位置する葉山の方を水源とするようだ。一方、本流の朝日 川は西の大朝日岳が源頭らしい。朝日川は朝日鉱泉の所で東から北へと90度、方向を転じている格好だ。 |
 峠からの帰り道での写真 側に流れる川はヌルマタ沢 |
|
川の名が変わったが、道の名も変わるようである。白滝から朝日鉱泉までが西五百川林道で、朝日鉱泉から峠方向は黒鴨林道だと思う。ただ、その根拠が今で
は分らない。古いツーリングマップにその様に書き込みがしてある。かつて何かの看板ででも見たのだろうか。「黒鴨」とは峠を越えた白鷹町側の地名なので、
峠より白鷹町側だけの道の名前とも思われるが、何しろ林道標識が見付からない。見落としているのかもしれないが、途中に「西五百川林道」と書かれた標柱を
一本
見ただけである。 道は徐々に川筋から離れて行く。ヌルマタ沢に注ぐ 支流の川を渡り、小さな谷を詰め、段々と川の気配が薄れていく。 |
 |
 |
| 峠への登りが始まる |
|
いよいよ峠への本格的な登りが始まった。道はヌルマタ沢から支流のカジカ沢沿いへと移るが、もうほとんど山腹をよじ登る状態だ。視界がグンと広がる。これ
で峠への期待も更に高まる。やはり峠道はこうありたいものだ。閉塞された谷底の川沿いをクネクネ走っているより、山腹を登る方がやはり峠道を走っていると
実感でき
る。 |
 |
 |
|
道も川沿いのあの狭苦しさから開放される。路面は一部砂利道だったり、アスファルトが剥げた古い舗装路だったりするが、概して走り易い道だ。 |
 |
ヌルマタ沢本流の上流方向を望む (撮影
2012.11. 7)
ガードレールの代わりの駒止めが並ぶ
ガードレールの代わりの駒止めが並ぶ
|
だだ、高度が上がる割には、ガードレールが少ないのが気に掛かる。「駒止め」と呼ぶのだろうか、所々、路肩にブロック状のコンクリートが並んでいるのがせ
いぜいである。峠
がある東側の山稜とは大きな谷を一つ隔てて西の反対側に、雄大な朝日連峰がそびえている。高度を上げるに従いそれが見えてくるが、あまりよそ見をしていら
れない。道を外さないよう、慎重な運転を心掛ける。 |
 |
朝日連峰を望む (撮影
2012.11. 7)
 |
どういう訳か、峠に近付くほど、舗装路が新しくなった。真新しいアスファル ト路面である。ついでにガードレールも完備かと思ったら、ポストが並ぶばかりで、その間が繋がっていない。それでも何もないよりはましである。道路の改修 工事がどんどん進んでいるという雰囲気ではない。もうこの状態のまま、放棄されたような感じを受ける。 |
 |
登って来た道を
見下ろす (撮影
2012.11. 7)
|
道はダイナミックな九十九折りに差し掛かる。如何にも峠道らしい醍醐味を味わえる。振り返ると、朝日連峰の山々が目の高さに広がった。これが愛染峠の道の
味わいかと思われた。 |
 |
朝日連峰を望む
(撮影
2012.11. 7)
やや雲が掛かる
やや雲が掛かる
| 峠 |
 |
愛染峠 (撮影
2012.11. 7)
手前が白鷹町、奥が朝日町
舗装と未舗装の境が峠だろうか
手前が白鷹町、奥が朝日町
舗装と未舗装の境が峠だろうか
|
さて、いよいよ愛染峠だと思ったら、目の前にガードレールのバリケードが現れて、行く手をふさいだ。何ということだ。これまで通行止を示す看板は何もな
く、
てっきりこのまま峠越えができるものと喜んでいたのに。 |
 朝日町側から見る |
 白鷹町側から見る |
|
さっぱり事態が飲み込めぬまま、とにかく峠周辺を散策する。天候はやや回復し、空が明るく一部に青空も見え出したが、峠を吹き抜ける風が轟々と恐ろしいほ
どだ。愛染峠と呼ぶ名前から想像していたやさしそうなイメージとは全く違う。 峠は、南北に連なる町境の嶺を、鋭角に横切っている。嶺はなだらかで狭い鞍部を越えるというような暗さは全くない。あまりにもあけすけに空が開けてい て、それがかえって峠らしさを感じさせない。 峠そのものは味わいに欠けるかもしれないが、峠の前後だけでなく、左右の稜線方向にも視界が広がり、一つの嶺を越えるという雄大さを体一杯に感じるロ ケーションだ。 |
 左奥に稜線沿いの道が分岐 手前左の分岐は峠横の展望広場へ |
 左の道が峠へ 右の道は展望広場に登る |
| 峠付近の様子 |
| 峠から北の稜線上に、道より一段高くなった草地がある。これが「愛染峠展望台」と呼ばれる広場のようだ。「ヌルマタ沢・野川 自然環境保全地域」と書かれ た看板などが、峠道を見下ろす位置に立つ。 |
 |
 奥に石段があり、その先に山小屋が建つ |
 |
 森林生態系保護地域の看板 (撮影 2012.11. 7) 森林生態系保護地域の看板 (撮影 2012.11. 7)(上の画像をクリックすると地図の拡大画像が表示されます) |
 ほとんど読めない |
 本地域は ヌルマタ沢・野川 自然環境保全地域です。 地域の自然と動植物を 大切に保護しましょう。 山 形 県 |
| 林道開通記念の碑など |
 尾根上の高みから望む この左側が白鷹町 |
 尾根上の高みから望む この右側が朝日町 |
| 展望広場の東側の端、白鷹町を一望する位置に一際大きな石碑が風を受けて立っている。峠の碑かと思ったが、残念ながら林道の開通記念碑であった。「黒鴨林 道開通記念」と表題にあり、碑文にはその林道開発の趣旨などが記してある。碑文の最後に書かれた日付は昭和46年10月だ。なかなか古い。また石碑の裏側 に工事経過が書かれてあり、昭和46年に「峰越林道黒鴨線」とある。 |
 |
 黒鴨林道完成記念の碑図 (撮影 2012.11. 7) (上の画像をクリックすると碑文が拡大表示されます) |
| 林道開削が奥地林の開発や朝日連峰の観光開発にあり、また「峰越林道」とも
呼ばれたことから、やはりこの黒鴨林道とは、白鷹町側から登って愛染峠を越え、朝日連峰の登山基地である朝日鉱泉にまで至る道を指すようだ。そんな道が昭
和46年には既に完成していたというのは驚きである。 記念碑の近くに木柱が一本、ポツンと立っている(右の写真)。何かの標柱だと思うのだが、木の表面は荒れて、文字の痕跡さえも確認できない。ここに「愛 染峠」とでも書かれてあったら、峠を探訪する者にとっては記念となる存在なのだが。 |
 |
| 展望 |
| 展望広場は稜線上に位置するが、白鷹町側の方に眺めが広がる。朝日町側はやや木々が多く、あまり見通しが利かない。黒鴨林道の完成記念碑は、その白鷹町側 の景色 をバックに堂々と立っている格好だ。 |
 |
 |
 |
 |
 |
白鷹町側の眺め (撮影
2012.11. 7)
| 峠名について |
|
さて「愛染」(あいぜん)である。この峠の名前は峠のどこにも見られない。文献などでも、さすがにこんな険しく寂しい林道の峠について、記述しているのは
見付からなかった。「愛染」で思い出すのは、古い映画に「愛染かつら」と題したものがあったということくらいだ。かつら(桂)は木の名になる。 結局、ネットを参考にすると、林道開通に伴い峠に愛染明王を祀ったそうだ。それで愛染峠となった。展望広場から少しの石段を登って稜線上を北へ行くと、 石造りのしっかりした山小屋があり、更にその奥にお堂がひっそりとある。訪れた時はシャッターが下りていて何も見えなかったが、そのお堂の中に愛染明王が 祀られているそうだ。シャッターは冬の積雪に備えた物だろう。それにしてもお堂は車道からは離れて見えない位置にあり、峠を訪れる者がこのお堂に気付くこ とは稀だろうに。 |
 |
 残念ながらシャッターが降りている |
| 峠からの帰り道 |
 |
峠からの帰り道
(撮影 2012.11. 7)
なかなか楽しい林道走行になる
なかなか楽しい林道走行になる
 |
 |
 |
峠からの帰り道 (撮影
2012.11. 7)
| 峠道はもう紅葉の最盛期を過ぎ、これから訪れる厳しい冬を前に、じっと強風
に耐えているようであった。相変わらず天候はさえない。どんよりと曇った空の下に、朝日連峰の山並みが見渡せる。冬期にはこの山々は白一色となり、人を寄
せ付けない世界となるのであろう。 朝日鉱泉から峠までの行き帰りに、2台ほど車とすれ違った。白鷹町へは抜けられないこの峠道に、一体何をしに来たのだろうか。まあ、先方もこちらを不審 がったに違いないが。それにしても、峠の通行止はどういう訳なのか。 |
 |
| 通行止の看板 |
|
朝日鉱泉の前の駐車場まで戻り、もう一度通行止の看板などがないことを確認した。ふと見ると、看板らしき物が伏せて倒されている(下の写真)。持ち上げて
覗いて見ると、そこに「全面通行止」と大書してあるではないか。また、その看板からロープが道の反対側にまで張られてあった形跡がある。 |
 峠方向に見る 倒れた看板があり、それを起してみると・・・ |
 |
|
誰かが峠方向に侵入する為、この看板を倒し、そのまま放置しておいたのだろうか。そうでなければ何の予告もなく峠で急に通行止のゲートが現れる筈がない。
白鷹町側の道の事情は分らないが、少なくとも朝日町側の朝日鉱泉前から峠までの区間は、本来は通行止となっているようだ。18年前に来た時と、事態は何ら
変わらないのであった。 もし、無責任にも誰かが通行止の看板を倒したままにしておいたのなら、これは大変迷惑な話だ。しかし考えようによっては、このお陰で愛染峠を訪れること ができた訳である。全面通行止の看板が立ち、道にロープが張られていたら、朝日鉱泉から先には進まなかっただろう。何だか複雑な気持ちである。 |
| 木川の分岐から市街地方向 |
 狭い |
もう、峠を訪れてしまい、後は余談となるが、一応木川の分岐から市街地方向
の道も辿っておく。 朝日川の左岸に沿う狭い道である。1994年に訪れた時は、まだ未舗装区間を残していた。県道白滝宮宿線になる前は、町道朝日線と呼んだようである。 古いツーリングマップには木川の分岐近くに集落を示すマークがあるが、私が訪れた時はもう人家は見られなかった。ぶな峠を越える大規模林道が開削された 時、その痕跡さえも消え去ったのかもしれない。文献にも朝日町大字立木(たてき)内の木川、一ツ沢、荒沢の集落は姿を消したとある。この付近は積雪3mに も及ぶ、冬の生活が厳しい地域とのこと。余程の標高かと思ったら、400m程度だ。私の新居は324mで、さほど変わりないのであった。 |
| 人家はないが、沿道に石碑なども見られ、朝日鉱泉付近の登山や木材運搬用の
道とは、やはりやや趣が違う気がした。 木川の分岐から1km程も下ると、朝日川の本流に木川ダムが架かっている。昭和33年完成とのこと。右岸に木川沢と呼ぶ沢が流れ込んでおり、それが名前 の由来らしい。ダムから下流へと導水管が設けられ、発電を目的としたダムだ。このダムの完成の後、更に朝日鉱泉付近を取水口とする水路式の朝日川第二発電 所が建設されたそうだ。 |
 |
 |
道は尚も朝日川の左岸を下る。この朝日川の上流域は朝日町の大字で立木と白
倉と呼ばれる地域だ。それぞれ江戸期から続いた村で、明治22年に他の村と合併して西五百川村(にしいもがわむら)となった。西五百川林道はこの村名
から来ているのだろう
か。更に西五百川村は昭和29年に合併して現在の朝日町になっている。 立木と白倉の区分けは複雑である。概ね木川ダム付近の朝日川右岸側が立木で左岸側が白倉だ。しかし、左岸にある木川集落は立木となるようだ。また白滝 より上流域はほとんどが白倉で、愛染峠は白倉にある。しかし、朝日鉱泉の付近は立木の飛び地のようになっているらしい。 |
| 立木橋 |
| 道は蛇行する朝日川に沿って屈曲する。すると一本の橋を渡る。立木橋だと思 う。この橋より上流域が投網禁止と言われている橋だ。明治12の県統計表に立木橋の記述が見られるそうで、その頃にはもうここに橋が架かっていたらしい。 立木村の時代である。勿論今は架け替えられているのだろう。 |
 |
 左が一ツ沢への道、右が立木橋を渡って愛染峠へ 道路標識には左:一ツ沢、直進:白滝(朝日鉱泉)とある |
立木橋を渡って間もなく、右後方へ分岐がある。入口に「林道交通安全」と書 かれた緑の旗がはためき、側に「一ツ沢林道」の標柱が立っている。分岐の道路標識には、その林道方向に「一ツ沢」、立木橋を渡る県道方向に「白滝(朝日鉱 泉)」とある。昔はその一ツ沢林道の奥に、一ツ沢と呼ばれる集落があったようだ。 |
| 立木橋以降は朝日川右岸の道である。尚も狭い道が続く。川が近く、直ぐそこ に川面を 見る。雨天のせいか、水かさが増している。強い流れが川床の大きな岩を食み、白波を立てている。目を引くちょっとした渓谷である。これが真夏なら涼しい風 景だが、雨の晩秋には寒々しいばかりだ。 |
 川が近い |
| ゲート箇所 |
 |
やっと川沿いの狭い道から開放される時が来る。前方にゲート箇所が現れ、そこを過ぎると2車線の広い道となる。左に朝日川を渡って「Asahi自然観」へ の道が延びる。 |
| Asahi自然観への道は立派だが、愛染峠へと続くゲート箇所のある方を見
ると、如何にも寂しい道である。ゲート脇には「大型車通行止 落石
注意」とか「熊出没」といった看板が
立ち並ぶ。路上に掲げられた道路情報の看板には次のようにある。 道路情報(冬期閉鎖区間) 一般県道 白滝宮宿線 この先 西村山郡朝日町立木から 西村山郡朝日町白滝までの 9.2Kmは冬期間、積雪・雪崩のため (通行止)となります。 当然ながら白滝より先も通行止だろうが、県道としての区間は白滝までである。 |
 見るからに寂しい道 |
 この左にAsahi自然観への道が分岐 ゲート手前で分岐するAsahi自然観への道には、いろいろな案内看板が立っている(右の写真)。朝日町市街から続いてきているこの県道も、Asahi 自然観の為にあるようなものだ。 |
 |
 大きな案内看板が立つ 三本杉峠を越えてやって来た |
1995年に訪れた時は、北側の大江町より三本杉峠を越えて来た。ツーリン
グマップに一本線で書かれていて、車が通れるかどうかも分らない峠道だった。その三本杉峠の朝日町側に、かつて荒沢集落があったようだ。
三本杉峠を朝日町側に下って来ると、朝日川の左岸沿いの道に出る。それを少し遡るとAsahi自然観への道に突き当たる。Asahi自然観へは入り込ん だことはないが、1995年当時には既に道が整備され、大きな案内看板が立っていた。スキー場やその他のスポーツ施設があるようだ。 |
| ゲート箇所より下流 |
| Asahi自然観への分岐を過ぎると快適な県道で、車での移動がはかどる。
側を流れる朝日川も川幅を広げ、ゆったり流れ出す。 ゲートから4km程も来ると、太郎橋で朝日川を渡る(右の写真)。ここに来てやっと空が晴れ、西日が差した。峠では天候が悪かったのに、皮肉な話であ る。 その先、道は太郎トンネルをくぐって県道(主要地方道)9号に突き当たる。県道9号は最上川の左岸沿いを走る幹線路だ。対岸には国道287号も通じる。 この 近くで朝日川も最上川に注ぎ込み、これで愛染峠の道は終点である。 |
 ここに来てやっと空が晴れ、西日が差した |
| <余
談> 越えられるかと思った愛染峠が越えられず、大きなコース変更を余儀なくされた。今夜の宿もまだ決まっていない。もうあの二見屋はないのだ。県道9号を走 りながらも、宿の心配で頭が一杯である。路肩に駐車 スペースを見付け、携帯電話をかける。やっと宿の予約が取れた。しかし、もう夕方近くで、夕飯の準備ができないとのこと。仕方なく宿の一室でカップうどん とカップそばの夕食となった。これでは野宿の時と同じではないか。まあ、これも旅の一つの思い出ではあるが。 |
|
朝日町側の通行止の看板が倒されていて、曲りなりにも愛染峠を訪れることができたのは、それなりに収穫だった。考えてみると、これまで白鷹町側からは一度
もアクセスしたことがない。朝日町側に峠が多いからだったり、旅程が合わなかったのがその理由だ。白鷹町側の黒鴨林道も通行止の可能性が高いと思っていた
が、意外と通れるのかもしれない。これまで愛染峠はなかなか辿り着けない峠と勝手に思い込んでいたが、これはまた東北を旅して確認しなければと思う、愛染
峠であった。 |
| <走行日> (1994. 8.18 朝日町からアクセスするも、通行止の看板を見て諦める ジムニーにて) (1995. 8.17 朝日町からアクセスするも、朝日鉱泉から先、通行止 ジムニーにて) ・2012.11. 7 朝日町側で峠まで往復 パジェロ・ミニにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典 6 山形県 昭和56年12月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2012 Copyright 蓑上誠一>
|


